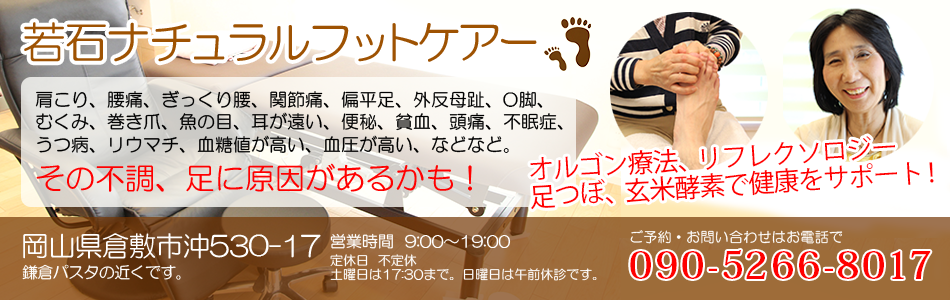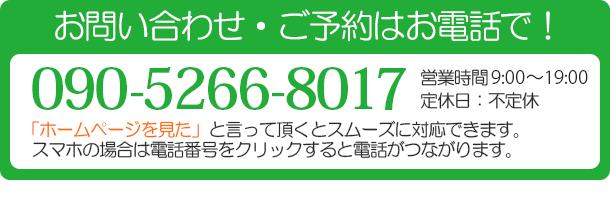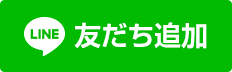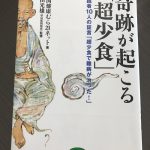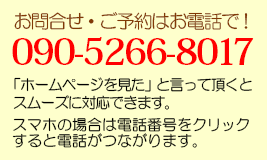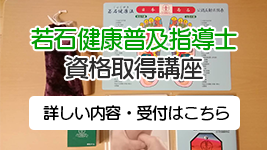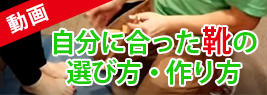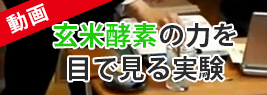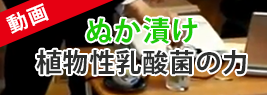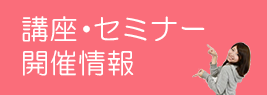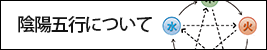本当に体に良い食べ物、悪い食べ物とは?
ステーキを例にとると、これを30年来、肉から遠ざかっていて、これを死ぬ思いで食べる人と、これを食べるとスタミナがつくと考えて喜んで食べる人とでは、栄養状態が異なってきます。
食べる時の精神状態や咀嚼の度合いが違います。それは人によって消化液の分泌量が違うからです。
消化液にはいろいろな種類があり、唾液にはじまって、その唾液の中の酵素の活性度、胃から分泌される酵素の活性度、胃液の分泌量、十二指腸および膵臓から分泌される消化液、胆汁など、人によってみな異なっているので、同じ物を同じ量食べても、食べる人が違えば栄養価も違ってきます。
食べ物の中にビタミンがあるかないかではなく、その人の腸内細菌の中に乳酸菌がどれくらいいるかが、栄養問題として重要です。
その反対にアノイリナーゼ菌はビタミンB1破壊酵素をもっています。肉食したり、甘い物をどんどんとると、腸の中でこのアノイリナーゼ菌が繁殖してきます。
例えば、ある野菜の中にビタミンがたくさん含まれているからということで、それを食べたとしても、腸の中にアノイリナーゼ菌がいっぱいいると、腸の中に入った野菜のビタミンはゼロになってしまうことさえあります。
お茶の水クリニックの故森下敬一先生は、より早く的確に治癒させるために患者の血液状態や内臓の機能状態を調べその人の体質に合った食べ物の処方箋を書き、正しい食事方法にすると、血液はどんどん正常化してくると同時に、肝臓・腎臓・自律神経の機能も回復してくるのだとおっしゃっています。
体の一部を切ったり、または薬(化学薬剤)を遣ったりする現代医学療法に比べ、食事療法がすぐれているのは、病気を治すとともに体質を改善し、その他の慢性病にかかりにくくするという点です。
出典:『クスリをいっさい使わないで病気を治す本』(森下敬一)より
【LINEで健康に関する情報を配信しています】
★LINE@に登録して頂くと、LINE@から簡単に予約することができます★
LINE@に登録していただいた方全員に「足の反射区療法をオススメする3つの理由」を無料でプレゼントします! 登録後すぐにご覧いただけます。
※友だち追加ボタンをクリックしても登録できない場合は、下のQRコードを読み込んで登録してみてください。

※すでにLINE@に登録していただいている方へ
2023年3月にタブレットが故障してしまいLINE@の管理ができなくなりました。
新しいLINE@を作成しましたので、2023年3月以前にご登録いただいた方は、お手数ですが上の「友だち追加」ボタンまたはQRコードからご登録をお願いします。
タグ:食生活の改善